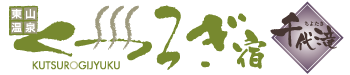ブログ
清龍寺 文殊院にまつわる伝説 「文珠童子」
2025/02/08

東山温泉から約14kmにある会津美里町高田地区に
「お文殊様」と呼び親しまれている「清龍寺 文殊院」があります。
文殊院は清龍寺内にある文殊菩薩を祀ったお堂で
古くから人々の信仰を集めていました。
文殊菩薩は、「三人寄れば文殊の知恵」ということわざで知られていますね。
すぐれた智恵を持ち、お釈迦さまの教えを経典にまとめたといわれます。
正しく見極める力を意味する「智慧」を司る仏様で
学業成就などのご利益があるとされています。
毎年2月25日は文殊院の例大祭「文殊大祭」で、
県内外から学問成就・技芸上達を願う人で賑わいます。
■会津に伝わる伝説 「文珠童子」
会津の富岡に大口大領という長者がおり、
文殊堂におさめる仏像をつくろうと願をかけた。
満願のちょうど七日目のこと、大領の前に、こどもの姿をした文殊菩薩が現れて
「お前の所望する像は、長井の田んぼにあるえの木であるぞ。」とおっしゃった。
この木は鳥やけものが近づくとたちまち死んでしまうことから
霊木とおそれられていた。大領が木を切ろうとすると村人たちは反対した。
しかし大領は、「文珠様のお告げできるのだから、おそれはせぬ」と言って
その木を切り、京都にはこんだ。
大領は毎日仏師を探し歩いたが、霊木にのみを入れることは、
おそれおおいと誰も応じてくれなかった。
大領が困っていると、童子があらわれて
「ワタシハ仏師デハナイガ、フタツノチカイヲマモッテクレタナラ、
仏サマヲツクッテアゲヨウ。」と言った。
大領は二つの誓いを守り、仮屋をつくってのぞき見せずに、二十一日間祈願した。
おそるおそるとびらを開けると、七尺五寸の仏様が黄金の光を放っていた。
大領がふし拝んでいると、仏様のかたわらの杖を手に
かさをかぶってすたすた歩き出し、大領はあわてて後を追った。
方角は会津の方だった。
何日か過ぎて岐阜県の赤坂までくると、
「ワタシハ奥州ヘハ行カナイ。高田ニハ文殊菩薩ガオラレルカラ、
美濃ノ国ノ谷汲山へマイルゾ。」とおっしゃって山の中に入っていってしまった。
谷汲山には豊然上人がいて、大領に力をかし、その仏様をお祀りした。
参考文献:「やさしく書いた会津の伝説」(村野井幸雄著・歴史春秋社)
■青龍寺 文殊堂 例大祭
住所:青龍寺 会津美里町字文殊西3611
毎年2月25日
参拝時間:午前8時~午後7時30分
「お文殊様」と呼び親しまれている「清龍寺 文殊院」があります。
文殊院は清龍寺内にある文殊菩薩を祀ったお堂で
古くから人々の信仰を集めていました。
文殊菩薩は、「三人寄れば文殊の知恵」ということわざで知られていますね。
すぐれた智恵を持ち、お釈迦さまの教えを経典にまとめたといわれます。
正しく見極める力を意味する「智慧」を司る仏様で
学業成就などのご利益があるとされています。
毎年2月25日は文殊院の例大祭「文殊大祭」で、
県内外から学問成就・技芸上達を願う人で賑わいます。
■会津に伝わる伝説 「文珠童子」
会津の富岡に大口大領という長者がおり、
文殊堂におさめる仏像をつくろうと願をかけた。
満願のちょうど七日目のこと、大領の前に、こどもの姿をした文殊菩薩が現れて
「お前の所望する像は、長井の田んぼにあるえの木であるぞ。」とおっしゃった。
この木は鳥やけものが近づくとたちまち死んでしまうことから
霊木とおそれられていた。大領が木を切ろうとすると村人たちは反対した。
しかし大領は、「文珠様のお告げできるのだから、おそれはせぬ」と言って
その木を切り、京都にはこんだ。
大領は毎日仏師を探し歩いたが、霊木にのみを入れることは、
おそれおおいと誰も応じてくれなかった。
大領が困っていると、童子があらわれて
「ワタシハ仏師デハナイガ、フタツノチカイヲマモッテクレタナラ、
仏サマヲツクッテアゲヨウ。」と言った。
大領は二つの誓いを守り、仮屋をつくってのぞき見せずに、二十一日間祈願した。
おそるおそるとびらを開けると、七尺五寸の仏様が黄金の光を放っていた。
大領がふし拝んでいると、仏様のかたわらの杖を手に
かさをかぶってすたすた歩き出し、大領はあわてて後を追った。
方角は会津の方だった。
何日か過ぎて岐阜県の赤坂までくると、
「ワタシハ奥州ヘハ行カナイ。高田ニハ文殊菩薩ガオラレルカラ、
美濃ノ国ノ谷汲山へマイルゾ。」とおっしゃって山の中に入っていってしまった。
谷汲山には豊然上人がいて、大領に力をかし、その仏様をお祀りした。
参考文献:「やさしく書いた会津の伝説」(村野井幸雄著・歴史春秋社)
■青龍寺 文殊堂 例大祭
住所:青龍寺 会津美里町字文殊西3611
毎年2月25日
参拝時間:午前8時~午後7時30分
 谷汲山 華厳寺の鬼
谷汲山 華厳寺の鬼
現在、この仏様は岐阜県 谷汲山 華厳寺にお祀りされており
西国三十三所第33番満願霊場として
地域の方に、「谷汲さん」の愛称で親しまれています。
この伝説は、谷汲山 華厳寺の縁起としても記されており
大領の願いが、西国三十三所の33番に通じていくとは驚きました。 龍門寺 文殊院は、元は会津総鎮守の伊佐須美神社の境内にあり
龍門寺 文殊院は、元は会津総鎮守の伊佐須美神社の境内にあり
寛文年間(1661~73)に社地から分離し、伊佐須美神社奥の院別当を
つかさどっていました。 伊佐須美神社には、春になると樹齢120年といわれる御神木の薄墨桜が
伊佐須美神社には、春になると樹齢120年といわれる御神木の薄墨桜が
会津五桜として人々を癒し愛されています。
毎年4月29日にはこの桜樹の霊を祀る花祝祭が行われ、
サクラの花びらを入れた餅をついて祝います。
伊佐須美神社 御神木 淡墨桜 (例年の見頃は4月下旬頃)